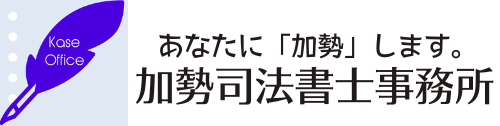本日の日経新聞に、山内洋嗣弁護士による「コンプラ過剰対応に注意」という記事が掲載されていました。

行きすぎたコンプライアンス対応が企業の萎縮を招くリスクを指摘する内容です。企業法務に携わってきた立場から、この問題について考えてみます。
リスクがある=やめる、ではない
法務部門はあくまで事業部門に対してリーガルリスクを判断材料として提供する部署です。
ところが実務の現場では、法務にある意味「決断」を求めてくる事業部門担当者も少なくありません。
「法務がダメと言っています」――こうした言葉が社内で飛び交っているとしたら、それ自体がオーバーコンプライアンスの兆候かもしれません。
完全に違法な事柄はともかく、リーガルリスクがある=その案件をやめる、ということにはなりません。
リスクを把握した上で、事業の成長性や将来性といった他の要素も含めて総合的に判断する。これが本来の意思決定のあり方です。
記事にある「自社の競争力維持とコンプラの調和」とは、まさにこのことを指しているのだと思います。
「法務確認済み」という落とし穴
もう一つ、私が会社員時代に経験した事例をご紹介します。
ある会社で、稟議書にすべて「法務確認済み」と記載するよう求める慣行がありました。
この慣行ができた背景には「法務の確認が漏れがちだった」という事情があったのでしょう。その問題意識自体は正しいものです。
しかし、稟議書に「法務確認済み」と書かせることは、法務が案件にお墨付きを与えているような印象を生みかねません。
先ほど述べた通り、法務の役割はリスクという判断材料を提供することであり、案件の可否を決定することではありません。
法務確認が特別視されることで、むしろオーバーコンプライアンスを助長してしまう恐れがあるのです。
必要なのは「仕組み」を整えること
では、法務確認が漏れないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
「稟議書にはすべて法務確認済みと記載すること」といった一律のルールを設けるのではなく、どのような案件で法務確認が必要かを明確にし、業務フローの中で自然に確認が回る仕組みを作ることが大切です。
法務の役割を正しく理解し、それを仕組みとして組み込むこと。これがオーバーコンプライアンスを防ぐ鍵であり、記事にある「襟を正すことと、イノベーティブな発想で競争力を高めることの両立」につながるのではないでしょうか。